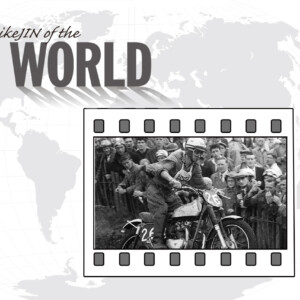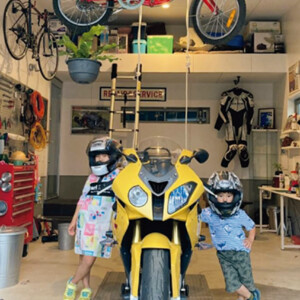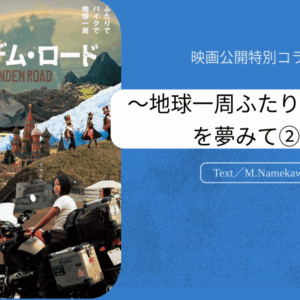懐かしいオフロードバイクカタログ【YAMAHA Tenere Series】
ヤマハのテネレの歴史がわかる全モデルを真面目なようで、ちょっとだけカールのように軽い感じで説明。ワイルドサイドを走るイメージからアドベンチャーになるまで。箸休めページとして読んでください。
TEXT/F.Hamaya 濱矢文夫
テネレは続いている
80年代からヤマハが使ってきた“テネレ”とは、トゥアレグ族の言葉で「何もないところ」の意味。ニジェール北東からチャド西部のサハラ砂漠の中南部をテネレ砂漠と呼ぶ。
「私が冒険の扉を示す。開くのは君だ。望むなら連れて行こう」という有名な言葉を残した故ティエリー・サビーヌが70年代後半にはじめたパリ・ダカールラリーで、この砂漠は難所のひとつになっていた。この時代は本当の“冒険”がまだ目の前にあったように思う。世界中の隅々まで人間がたどり着き、インターネットでその様子が見られる現代とは、砂漠を走るラリーのあり方が違っていた。
昭和の頃は「テネレ」という単語にワクワクしたものである。間違って「テレネ」と覚えていた人もいたけれど、テネレ=ヤマハ=砂漠の冒険をイメージさせるバイク。現代のテネレであるテネレ700がオフロード走行にこだわっているのは、その伝統ある名を受け継いだから。1983年の初代から40年以上、テネレ砂漠に行ったことがなくても、ヤマハのテネレはずっと僕らの心をワクワクさせてくれる。
1983:XT600 Ténéré
市販版テネレの歴史はここから。ご先祖様は第1回大会、二輪と四輪を合わせてシリル・ヌブーが優勝したときに乗っていたXT500。日本車ビッグタンク列伝ならば、前年の82年にホンダXL250Rパリ・ダカールが発売されていたが、これはいわゆるパリダカマシンのイメージ戦略商品。長い満タン航続距離ツーリングには役立ったけれど。
ヤマハXT600はそれとは異なり、ちゃんとパリ・ダカールに出るためのベースマシンとしての使命を背負った機種だった。空冷単気筒エンジンは、これ以前のXT550から引き続き負圧式キャブと強制開閉式キャブをセットにして、低速から高速域の特性を良くしたYDIS(ヤマハ・デュオ・インテーク・システム)を採用。アルミスイングアームにモノクロスサス、そしてディスクブレーキと最新装備。
範馬勇次郎の筋肉みたいにもっこりした燃料タンクは34L。これが冒険レースの発火点である欧州市場でカルト的な支持を得た。


1988:XT600Z Ténéré
80年代、国内では空前のバイクブームがやってきた。パリダカの認知度が上がり、TV放送があり、カップヌードルのCMにパリダカの映像が使われ、第1回パリダカの頃に「ニンドスハッカッカ! マー! ヒヂリキホッキョッキョ!」と言っていた少年少女も免許が取れる歳になり、砂漠の冒険レースに憧れた。
パリダカはどんどん高速化し、大きなフェアリングを身にまとうようになった。市販車ベースではなく専用レーサーとして作られたホンダのNXRが86年から88年まで3連覇。そのイメージのXRV650アフリカツインが発売された年に、空冷4バルブ595cc単気筒のテネレにも2灯ヘッドライトのフェアリングが装着された。これはヤマハ車のパリダカ参戦を牽引していたフランス、ソノートヤマハのマシンをイメージさせるゴロワーズカラーであり、ロードレースではリーンウィズの貴公子、クリスチャン・サロンのイメージでもあった。
ちなみに88年のヤマハ製パリダカ単気筒レーサーは、本社ファクトリーが初めて開発した水冷5バルブシングルエンジンのYZE750テネレ(0W93)だった。


1989:XTZ750 Super Ténéré
砂漠のレースの高速化は多気筒化へとつながった。BMWはお家芸のフラットツインで3連勝、その後ホンダが水冷Vツインで3連勝。当時DUCATIを傘下にしていたカジバは、デスモドロミックの空冷2気筒を投入した。
ソノートヤマハチームを指揮していたジャン=クロード・オリビエはライダーとして、エディ・ローソンが乗って86年にデイトナのバンクをトップで駆け抜けたFZ750の水冷4気筒ジェネシスエンジンを搭載したマシン(FZ750テネレ)を砂漠に持ち込んだ。当時チェリーボーイだった筆者は「いやいや、それは無茶だろ」と思ったけれど、蓋を開けてみると━━━やっぱりダメだった……。
ヤマハはワークス単気筒マシンでトップ争いをするなど善戦はしたものの勝てず、本社では次のパリダカマシンを想定した水冷5バルブDOHC並列2気筒エンジンのXTZ750スーパーテネレの開発がスタートした。クランクは安定したトルクで押し出す360°。並んだピストンが同時に上下するためにどうしても出てくる振動には、2軸バランサーで対応した。フレームはダブルクレードルで、前が21インチ、後ろが17インチ。


1991:XTZ660 Ténéré
砂漠のレースが多気筒化する一方で、欧州市場では比較的安価で日常的に使いやすいミドルクラスの需要があった。そこで誕生したのが、アップライトなポジションで楽に乗れ、軽い単気筒で幅広い道に対応できるデュアルパーパスのXTZ660テネレである。水冷5バルブは、ワークスマシンYZE750テネレ(0W93)譲りとも言える。
ここには「レースで勝つ」という呪縛はない。21/17インチホイールで、燃料タンクはビッグではないけれど20Lあり、単気筒の燃費の良さを考えれば十分すぎる仕様だった。テネレの名は付いているものの、最初はダカールとは関係ないスタイル。トランプ大統領とトランプマンくらい違うイメージである。しかし後に、丸目2灯のパリダカレーサー風の顔つきに変わった。


2008:XT660Z Ténéré
XT600、XT600Z、XTZ660ときてXT660Z。とってもややこしい。テネレ初級者には名前だけでは判別がつかない。でも、こうやって写真で見るとまるで違う。2段ヘッドライトで、どことなくカオナシ風に見える顔のモダンなスタイル。
ショートストロークの水冷SOHC659cc単気筒エンジンは、5バルブをやめて4バルブに。キャブレターではなく燃料噴射を採用した。もはや“テネレ”の名はパリ・ダカールマシンレプリカではなく、ヤマハのデュアルパーパスモデルを指す言葉になった。
21/17インチホイールにアルミ製スイングアーム。22L容量の燃料タンクとは思えないほどスマートに見える。前後200mm前後のホイールトラベルで、デュアルパーパスとしての使い勝手はしっかり継承している。日本では正規販売されなかったのが残念だ。


2010:XT1200Z Super Ténéré
ヤマハからテネレという名が付いたバイクが登場した頃は、まだ“アドベンチャー”カテゴリーは存在しなかった。道を選ばず走れる排気量の大きいデュアルパーパスツーリングバイクとしてブームになるなんて、XTZ750スーパーテネレの時代には想像できなかっただろう。
スーパーテネレは2気筒を継承。ただしクランクは360°ではなく、現代のパラツインエンジンの主流である270°を採用。駆動はメンテナンスフリーで耐久性のあるシャフトドライブを備えた。砂漠のテネレがアドベンチャーに昇華したのだ。このマシン、ワインディングでもかなり身軽に走れてしまう。


2014:XT1200ZE Super Ténéré
XT1200Z“E”となって何が変わったか。EはElectricのE(たぶん、きっと)。電子制御のサスペンションになり、YCC-T(電子制御スロットル)も採用された。これにより、エンジン特性を変化させるモード(ヤマハD-MODE)が付いた。
XT1200Zスーパーテネレとは見た目以上に違うのである。進化を例えるなら、マジンガーZからグレートマジンガーに変わるくらいだ。