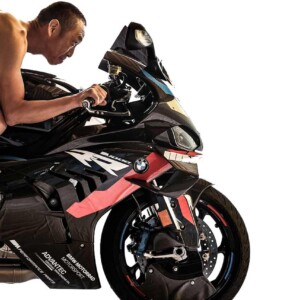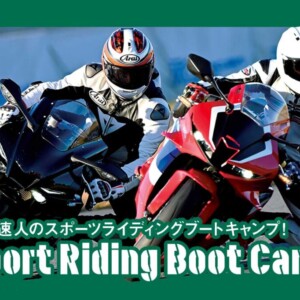ちゃんと使えてる? タイヤの性能を引き出すための3ステップを解説!
近年は温度依存性が低めのロードスポーツ用タイヤも増えてきたが、それでも適した領域まで温めないと、本来の性能は発揮させられない。コースインから数周の間に“やるべきこと”を中野真矢さんが伝授!!
上級者ほど慎重になるコースインからの数周
撮影などの仕事でサーキットを走るとき、特に注意しているのがコースイン直後。我々の場合は真冬でも走るので、かなりリスキーな状況のときもありますが、そうでなくても「思いがけない転倒」の多くは、タイヤが温まっていないことに起因して走行の序盤に発生するのです。
感覚的には、ヒザを擦れるようになるまでが〝予備ウォームアップ〞で、それを終えてからさらに熱を入れて、タイヤのフィーリングに自信を持てるようになるまでが、本当の意味でのウォームアップ。そして、実は本当に大切なのは、下で解説しているステップ1〜2に相当する、タイヤを〝慣らす〞段階なのです。
これは「タイヤが新品ではないから」とか「路面温度が高いから」とか「今日3本目の走行だから」などの理由で省いていいプロセスではありません。少なくとも2周、気温や路面温度が低めならさらに数周は、ぜひ取り入れてください。それにより、コースイン直後の転倒はかなり避けられるようになるはずです。
ヒザが擦れる程度のグリップを得られるようになったら、次の段階へ。とはいえ、いきなりハイペースを狙うのは危険です。適正なライディングフォームを意識しつつ、タイヤと身体をさらに温めて、ベストな状態だと確信が持てるまで、じっくり待ちましょう。
(中野真矢)
STEP1_表面を皮むきするくらいの感覚でタイヤを慣らしていく
人間の生活に例えるなら、朝起きてまずは顔を洗うような段階。なるべくマシンを立てたまま、タイヤを動かしてあげます。3
タイヤは、ストレートで荷重をかけることで温めるのが基本ですが、最初からいきなりワイドにスロットルを開けたり強くブレーキを握ったりすると、電子制御の有無や精度によってはタイヤのスピンやロックにつながることも……。
タイヤウォーマーがあるとこのステップ1をかなり短縮できますが、ライパ参加者の多くは自走組でしょうから、とにかく最初の2周は慎重に!!

何度か走ったタイヤでも走り始める度に行なう

「何かおかしい」という感覚は正解だったり

走行モードがあるなら優しい設定で走り始める
ライディングモードやトラコン介入度を切り替えられるなら、コースイン直後はややマイルドな出力特性か、早めに電子制御が介入する設定にしておく場合もあります。
STEP2_タイヤと車体の状態を観察してバンクを深めていく
ステップ1で最初のタイヤウォームアップを終えたら、次の段階では少しずつバンク角を増やしていきます。新品タイヤの皮むきと同じ要領で、接地範囲を少しずつ拡大。“ゆっくり温めつつ慣らす”段階です。
気温や路面温度が低いときは、ステップ1〜2の時間をより長くしてあげることが大切。タイヤを温めることに徹しながら、徐々にバンク角を増やし、中上級者の場合はヒザをギリギリ擦れるくらいを目指します。
コースイン直後の思いがけない転倒は、このステップ2でも起きやすいのでご注意を!!

先にリアタイヤから温めるよう意識する
前輪よりは後輪が滑る方が、立て直せる可能性は高いので、コースイン直後はリアの方がウォームアップさせやすいと思います。逆に言うなら、フロントが温まるまでは、浅めのバンク角で慎重に走りましょう!

フォームによってはグリップを感じにくい場合も
身体の動きが固まったような状態だと、タイヤの接地感を掴みづらい傾向。だから恐怖心が高まり、余計にウォームアップが進まず、なかなかグリップを引き出せないという悪循環に……

STEP3_ヒザが擦れる段階でも8割くらいで様子を見る
徐々にバンク角を増やし、ヒザが路面に接するようになると、不思議なことに少し安心感が生まれます。でも、まだまだ過信は禁物。
ここまではタイヤにとって“予熱”のようなもので、パフォーマンスを発揮させるために本当の意味で“熱を入れる”段階は、この先にあります。
タイヤウォーマーを使用すると、短い時間でステップ3まで到達できますが、だからといっていきなり100%の走りを狙うと、それこそタイヤに裏切られることも……。前後タイヤのフィーリングに絶対的な自信が持てるまでは80%で!

右コーナーが続いた後の左コーナーは要注意
トレッド表面は路面との摩擦で温度が上がり、走行風で下がるので、例えば袖ケ浦フォレスト・レースウェイの5コーナーなど、しばらく右コーナーと直線区間が続いた後の左コーナーは、安全マージンを多めに!!

路面温度が高くても3段階のプロセスは同じ
気温と路面温度が高いと、ウォームアップはだいぶ楽になりますが、だからといって省略していいわけではありません。真夏でもプロセスは同じ。確実にステップを踏んで、転倒を避けましょう。