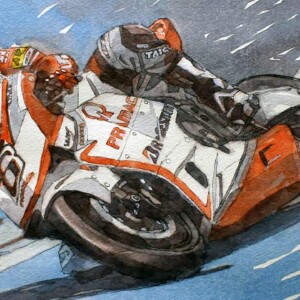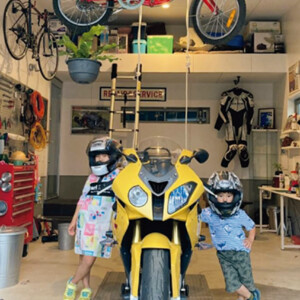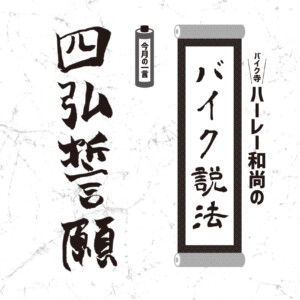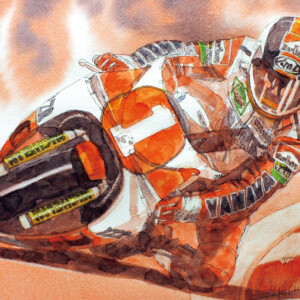【不定期連載】はめ殺し。懐かしいオフロードバイクカタログ【HONDA XL Series】
まじめではないカタログがやってきました。前回語らなかった、なぜ「はめ殺し」なのか、という理由を。それは、ずっと昔に付き合っていた帰国子女で日本語が上手ではない彼女が「あのさ、“はめ殺し”って、ものすごくイヤラシイ言葉だよね」と言ったことが衝撃すぎたので、それをタイトルにした次第。
TEXT/F.Hamaya 濱矢文夫
我らが青春のXLを懐かしむ
XLという車名はホンダトレールの代名詞。80年代はバイクブームだったからホンダXL、XLR──忘れちゃいけないXLXで、仕事場や学校に通ったり、林道行ったり、ちょっとしたエンデューロレースに出たり、彼女にふられたり、と思い出がいっぱいの人が多かろう。私の友人は橋の下で彼女とチョメチョメしているときにXLRのキックペダルを盗まれたりした。そんな青春のホンダトレールXLシリーズの歴史を振り返るたいへん不真面目なカタログである。
XLディグリーを入れなかったのはなぜか。ディグリーは「セローになりたかった僕ら」編として登場させようと思っているから取っておいた。
1975_XL250:まるでシートが「とらや」のようだ
最初の“XL”は125と同時に出た。羊かんのようなカタチをしたシートにもえもえきゅんである。この3年前に前身となるオフロード専用車のSL250Sを出していた。その輸出名がXL250だったから、そっちが先といえば先。2ストのエルシノアMT250がこのXLより前に出ていたから、オフロード専用車としてのインパクトには欠けるけれど。
しかしSLはアップフロントフェンダーだったのに、これをなぜダウンフェンダーにしたんだろう。「地下鉄の電車はどこから入れたの? それを考えてると一晩中寝られない」と同じくらい謎。とにもかくにも国内ではここからホンダXL物語は始まった。

1978_XL250S:とりあえず大きくすればいいのである
フロント23インチタイヤを履いたことからトレール史に残る革新的な1台となった。より大径にしたら走破性は上がるのは確かだ。胸になにかついているな、と思ったら乳首だったってくらい当然。フロントサスペンションを高性能にするより簡単。高速域ではジャイロ効果でまっすぐ進みたがっても気にしない。
タイヤの選択肢なんてのも気にしない。潔いほどホンダらしくて好きだ。なぜか夜中のファミレスで「じゃあさ、23インチにしたらよかね?」「いいねそれ」「それでいこう!」って睡眠不足ハイになって盛り上がるホンダの中の人を想像してしまった(そんなことはないだろうけど……)。

1981_XL250R:ナカタさんはXL250Rに乗った
なんの脈絡もなく当時のホンダリリースを村上春樹風にしてみた。
「ホンダは新しいバイクを出すことにした。名前は『XL250R』という。妙に無機質な名前だけれど、バイクにとって名前なんてそんなに大事じゃない。重要なのは、乗ったときにどう感じるか、どこまで行けるかだ。リアにはプロリンク・サスペンションが付いている。路面の変化に応じて、じわじわと、しなやかにショックを吸収する。まるで器用な猫の背骨のように。そして新しく設計されたフレームと、ちょっと出力を上げたエンジン(20馬力から22馬力へ)のおかげで、全体のバランスがいい。こういう数字の変化は、人生におけるささやかな朗報みたいなものだ」

1982_XL250R パリ・ダカール:砂漠を走るマシンがかっこよく見えた
XR500Rをベースに変速を5速から4速にして、ヘッドを加工してカムシャフトにベアリングを使い、φ94mmピストンで排気量を上げるなど改造されたHRC製XR550Rでシリル・ヌヴーがホンダに初めてパリ・ダカールでの勝利をもたらした年の夏に発売された。ヌヴーのマシンのように50Lとはいかないけれど、21Lもある燃料タンク容量は燃費の良い単気筒エンジンと組み合わされ、満タン航続距離550km以上とも言われた。
ガソリンが無くなる前にトレールのシートにお尻をいじめられて走るのに飽きて道の駅のベンチで寝っ転がりたくなる距離である。トリコロールカラー、白いオーバーフェンダーなども含め砂漠の冒険レースマシンスタイルにワクワクしたものだ。

1983_XLX250R:隠れ美人のような、そうでないような
XL250RとXLR250Rの間になんかあったような……と忘れている人が多いのがこれである。DBで言えば、亀仙人に姉(占いババ)がいたってことくらいマイナー臭が漂うが、その後ホンダ4ストローク250トレールで長らく使われたRFVCを市販公道モデルとして最初に採用した記念すべき機種である。
新エンジンにヘッドライトが角目になってシートが当時のモトクロッサーCRのように青いのに、仮面ライダーに例えるとライダーマンのように改造人間ではなく強化服着用といった感じ。

1985_XLR250R(MD16):モトクロッサー由来の赤備え
ホンダ4スト250トレールとしては息の長い存在で親しまれてきたXLR250R。多くの人の思い出に残る1台。40歳代後半から50歳代後半で、若い頃に林道好きだったなら、必ず近くにあったと思われる。そんな親しまれたモデルの最初は赤エンジンだった。デザイナーがなんか悪いものでも食べたのか、きまぐれオレンジ☆ロードだったのか。
赤エンジンといえば先に出ていたXLV750Rや同年発売のXL600Rファラオも赤エンジンだった。これがハードな使用や経年で色が剥げてきたらみすぼらしくなるのである。でも今となったら奇抜でナウなヤングにバカウケだと思うんだけど。だからCRF250Lも赤エンジンにしてください。よろしくお願いします。

1986_XLR250R(MD20):みんなが知ってるXLRになった
赤エンジンのMD16からたった1年ちょっとでモデルチェンジですよ。MD16はリアが17インチだったのよ、このMD20でやっと18インチになった。実はMD16 XLRになる前のXL250R、XLX250Rもリアは17インチ。
MD16からボアダウン、ストロークアップとエンジンにも手が入ってます。見慣れているのもあってデザイン的にも完成された感。

1987_XLR-BAJA:今にも喋りだしそうなつぶらな目
MD20からモデルチェンジしたMD22はBAJAからスタートした。橋本環奈並に「目がデカ」と思ってしまうデュアルヘッドライトの顔つきに目が奪われるが、リアがドラムからディスクブレーキになっていたりする。フロントフェンダーの前側がつや消し赤になっているのはヘッドライトの反射をおさえるため。お弁当が入りそうなテールバッグも素敵。
賢明な読者諸兄に今更、BAJAの名の由来を語るなんて釈迦に説法で、BAJA丸出し! なんちて──バカ丸出しのダジャレです、スミマセン……。歳を取るとダジャレを言いたくなる病に誰か病名をつけてください。そんなことより「天才バカボン」ってバカボンじゃなくパパが主人公なのはどうしてなんでしょう? 天才BAJAボン。

1994_XLR250R SPECIAL(MD22):シリーズ最後の特別仕様
BAJAが発売されたあとに通常版XLR250RもMD22化され、1990年でエキパイがステンレスになり、フロントフォークがカートリッジ化されるなどのマイナーチェンジを受けたあとに、このXLR250R SPECIALでシリーズは最後となった。ホイールの光輝仕上げアルマイト処理とかあるけれど、基本的にカラーリングが特別なモデルである。
スペシャルに思えるかどうかの反省会場はこちらです。ただ、なんだかちょっと欲しい。最後の特別仕様ってだけで欲しくなるのは日本人の性。いやライダーの業(カルマ)なのかもしれない。