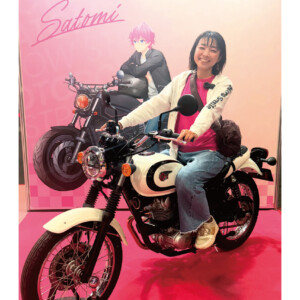今どき並列2気筒が面白い!それは何故なのか考えてみた
「JAIA輸入二輪車試乗会」で一気乗りした中でふと気づいたのが「並列2気筒」エンジンを採用したモデルが圧倒的に多いという事実。「何故なのか?」のギモンに自ら答えを導き出してみた
■ 単車倶楽部 2025年8月号
PHOTO:川井 晴稀 TEXT:ケニー佐川(佐川健太郎)
馬力を出すなら4気筒だが…
最近「並列2気筒=パラレルツイン」が流行っている。前述のJAIA一気乗りでも全18車種中15車種が2気筒(うち10車種が並列2気筒)だ。これは日本だけでなく世界的なブームのようだ。
でも何故?かつては大排気量バイクといえば4気筒が定番だった。もちろん、ハーレーのVツインやBMWのフラットツインなど、伝統的ブランドではエンジン形式そのものがアイデンティティになっている場合もあるが、近年まで高性能スポーツモデルは4気筒マシンのオンパレードだった。その証拠に究極の性能を争うレースでは常に多気筒化へと進んできたし、現代のMotoGPマシンも例外なく4気筒だ。その理由は明快で「パワーを稼げる」ためだ。多気筒化することで1気筒あたりの排気量は小さくなる代わりに、気筒数の分だけ爆発回数を増やすことが可能になる。1回あたりの爆発が小さく燃焼間隔も短くなれば振動や鼓動感は減るが逆に回転はスムーズになり、エンジン回転数もどんどん上げていける。つまり馬力を出しやすくできるメリットがあるのだ。
では何故すべてのバイクが4気筒にならないのか、というと主な理由は「大きく重くなる」からだ。たとえば単気筒ならシリンダーが1本だが4気筒だと4本になり、ピストンやバルブの数も同様に気筒数倍になり、カムやクランクのシャフトも長く、エンジンブロック自体が大きく重くなり、それを支える車体も頑丈に作る必要が出てくる。また、機構が複雑になり製造コストも高くなるし、一般的に燃費も悪くなるなどデメリットもけっこう多い。まあ、メーカー側の本音としては作るのが大変なのだ。


Vツインの良さを並列で再現
そこで本題。ここにきて何故に並列2気筒を採用するメーカー(マシン)が増えたのか?自分も含め、最速マシンが全盛期だった21世紀初頭を懐かしむ昭和世代も多いとは思うが、最近は環境配慮も必要だし、ガソリン代も高止まりだ。相変わらず2輪がらみの交通事故も多いし、だいたい「最速」とか「最強」という言葉が時代の空気に合わなくなってきたと思う。純粋なモータースポーツとしてのサーキット走行は別として、街乗りやツーリングをもっと気軽に楽しみたい、スピードや馬力ではなく質の高い走りを追求したいライダーが増えてきたのではないかと思っている。
そんなライダーの趣向に寄り添うのが並列2気筒かも。最近ではエンジンの幅も単気筒並みでスリムかつ車体を軽くできるし、Vツインと比べても前後長が短く、マス集中化もしやすくフロント荷重も稼ぎやすい。パワー的には4気筒に劣るが、取り回しやすさやハンドリングの軽快さなど、バイクを扱いやすく運動性能を高められる要素が詰まっているのだ。また、コンパクトさ故に車体設計に余裕ができるため、様々なセグメントの車種にも転用できる。たとえば、今回JAIAで試乗したハスクバーナの「ピットピレン801」と「スヴァルトピレン801」に搭載されるエンジンは元々KTM「790デューク/アドベンチャー」用に開発されたLC8cがベースだし、その後890シリーズを経て最新の「990デューク」へと継承されている。国産ではヤマハ「MT-07」「YZF-R7」「テネレ700」。スズキでも「GSX-8S」「Vストローム800DE」で同じエンジンを共有するなど、並列2気筒は国内外のミドルクラスで幅広く採用されている。
そして、もうひとつ大事なメリットとして出力特性がある。今ほとんどの並列2気筒は「270度クランク」を採用している。2つの気筒での爆発間隔を270度位相(ずらす)することで、Vツインにも似た小気味よい鼓動感と路面をつかむトラクション感覚を実現しているのだ。実際に不等間隔爆発とすることで、特に雨天などではタイヤのグリップ感が分かりやすいし、バランサーを併用することで一次震動をほぼゼロにしてスムーズな回転フィールを得られるなど、簡単に言えば「Vツインの良さ」をよりコンパクトな並列2気筒で再現できるわけだ。
余談だが、かつてWGP(今のMotoGP)が2スト500㏄マシンだった時代に、従来の等間隔爆発ではなく位相同爆(爆発間隔を微妙にずらした)に改めたホンダNSR500で当時の世界王者、ミック・ドゥーハンが勝利の山を築いた話はあまりに有名。これも主目的はトラクションを得やすいから。当時でも200馬力を超えた2ストの凶暴なパワーを、まるで脈を打つように路面を伝えることでスリップを抑え、ライダー側も滑り出しの感覚をつかみやすかったという。
今のストリートモデルに搭載される並列2気筒270度位相クランクも、ドドン、ドドンと馬が路面を蹴って疾走するギャロップにも似たリズムによって、ライダーはタイヤが路面と接地している感覚が分かりやすく安心できるし、その鼓動感がまた親しみやすさを生むわけだ。より動物的というか、人間には馴染みやすいリズムなのかもしれない。また近年の技術革新により、単なるパワーだけでなく、それを効率的に路面に伝えることで、安全に気持ち良く走る技術が市販車にも投入されてきた恩恵も少なくないだろう。コンピュータ制御のFIがかつての高性能キャブレター並みにスムーズに燃料を吹いてくれ、最適な点火時期をコントロールし、6軸慣性ユニットによる姿勢制御がコーナリング中でもABSやトラコンで安全な走りをサポートしてくれるようになった。
ということで、まとまりのない話になってしまったが、「並列2気筒」は軽量コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルでコスト的にも安くできるため、どんなモデルにも幅広く使えて、乗ったときのフィーリングも気持ちいいなどメリットが多いエンジンということ。そんなことをケニー佐川が言ってたな、と思い出しながら何かの機会に試乗してもらいたいと思います。



佐川健太郎
2輪ジャーナリストとして専門誌やWEBメディアで活躍する傍ら「ライディングアカデミー東京」校長を務める。交通心理士。バイクブームど真ん中世代!